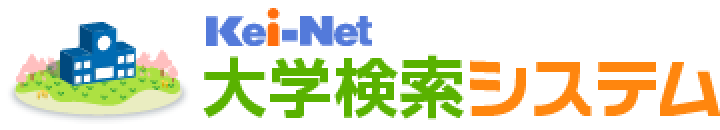東京都立大学大学からのお知らせ ゼミ研究室紹介
掲載している内容は、2020年6月時点のものです
経済経営学部 経済経営学科
荒戸ゼミ(計量経済学/応用経済学)
<因果推論>の手法で
データを分析して原因を探る力を養う
ゼミの学び
原因と結果の関係を探るためのデータの集め方や扱い方を学ぶ
 ゼミで2年間過ごした仲間との卒業写真。
ゼミで2年間過ごした仲間との卒業写真。卒業後も約年1回のペースで同窓会を開催している
現代は、ビッグデータをはじめ、様々なデータを分析し、活用する時代だといわれる。データを扱う学問分野には様々なものがあり、計量経済学もそのひとつ。実験して確かめられない経済学の理論を、観察できるデータを集め分析することで、実証しようとするものだ。
「このゼミでは、データを扱う手法と基本の理論をまず統計学で学び、その延長として経済データを扱う計量経済学を勉強します」と荒戸寛樹先生。その計量経済学で今、研究者たちが熱心に取り組んでいるのが「因果推論」と呼ばれるもの。データを分析し、原因と結果を推測するのが因果推論だが、ただしデータを扱うには注意が必要だという。例えば、バスケットボール選手の体重と得点のデータから、体重の重い選手ほど得点力が高いことがわかったとする。それを見て“選手の体重を増やせば得点力がアップする”と判断していいだろうか?「身長が高ければ一般的に体重も重いわけで、バスケの場合、体重と得点力に相関関係はあっても、因果関係は疑わしいですよね。いろんな要因から決まる結果について、ひとつのデータだけを見て単純に考えてしまうと間違える。〈正しく原因を推測していくには、どうデータを取って、どう分析したらいいのか〉という計量経済学の課題もゼミで勉強します」
ゼミの特徴
フランクに話せる関係のなかでデータの見方・扱い方を学ぶ
ゼミはインタラクティブになってこそ充実したものになる、という先生の考えのもと、荒戸ゼミの時間は週2回、昼休みを挟む2コマ連続で設定されている。時に昼食をともにしながら、自由な雰囲気のなかで、じっくり考え、話し合うことで、関係ができあがり、学びの質や効率も上がっていく。お菓子係やイベント係がいるのも、関係づくりのための工夫だ。
先生は、このゼミを通して学生に「データ・リテラシーを身につけてほしい」と願っている。「データの時代とよくいわれますが、逆にデータにだまされやすくなっているんじゃないかと思うのです。バスケの体重と得点のように、ただデータがあればよいわけではない。これまで学んできたことの蓄積を踏まえながら、データの使い方や見極める眼を磨くのが、大学の、ゼミという場ではないでしょうか。その力を身につければ、どんな場所でも、文字どおり生きる力になると思います」
研究の進め方

荒戸ゼミでは毎年夏合宿を行っている。この写真は長野県白馬で夏合宿をした際の川下りの風景。

4年生は卒業論文を書く人が多い。研究の成果は大学内外とのインターゼミナールで発表する。

今は対面でのゼミができないので、オンラインでゼミを行っている。
京都大学理学部卒業後、京都大学大学院経済学研究科修士課程修了。同博士課程修了。博士(経済学)。専門はマクロ経済学、情報の経済学。
その他のゼミ研究室紹介
- 人文社会学部 人文社会学科 福田研究室(表象文化論教室)
- 人文社会学部 吉田研究室(英文学)
- 法学部 法学科政治学コース佐藤ゼミ(現代日本政治)
- 法学部 刑法ゼミ
- 経済経営学部 森ゼミ(テキストマイニング)
- 理学部 生命科学科 進化遺伝学研究室
- 理学部 電子物性研究室(電子物性実験)
- システムデザイン学部 燃焼・推進工学研究室(航空宇宙工学)
- 都市環境学部 観光科学科 地理学研究室
このページに関するお問い合わせ
| 大学・部署名 | 東京都立大学 アドミッション・センター(入試課) |
|---|---|
| Tel | 042-677-1111 |
| admission-tmu@jmj.tmu.ac.jp |